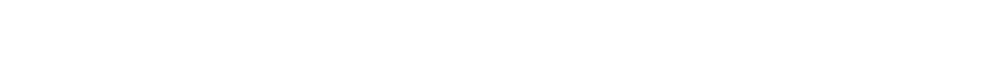「っぽいこと」をやめた瞬間、思考は始まる
-
田中大介という名前で語られる思考は、実のところ一人分ではない。
それは 田中友規と伊丹谷大介、二人の対話がぶつかり合うことで生まれる、
ひとつの思考の運動体だ。
その対話は、だいたい不機嫌な否定から始まる。
「それ、っぽすぎへん?」
「それAIが一番得意なやつやん」
今の時代、それっぽいものをつくるのは簡単だ。
Pinterestを見れば正解は並び、
AIに聞けば、もっともらしい言葉や構図が一瞬で返ってくる。
だからこそ、彼らはそこを疑う。
-
AIが悪いわけではない。
むしろ優秀だ。
問題は使う側だ。
バカが使ったら、そのAIもバカになる。
これは暴言ではない。
構造の話だ。
問いを立てられない人間がAIを使えば、
AIは問いを立てないアウトプットを量産する。
思考を放棄した人間がAIを使えば、
AIは思考停止を高速化する。
それだけのことだ。
-
「っぽい」という言葉は、この構造と相性が良すぎる。
それっぽい色、それっぽい言葉、それっぽい世界観。
誰かが決めた平均値をなぞることで、
自分で考えなくて済むし、責任も引き受けなくていい。
AIは、この「考えなくていい状態」を、
とてつもない速度で実現してしまった。
結果、世界は“正解っぽいもの”で溢れている。
-
田中大介がよく持ち出すのが、葬儀の話だ。
葬儀には葬儀っぽい型がある。
静かで、厳かで、誰もが想像できる形式。
AIに聞けば、その正解はいくらでも出てくるだろう。
だが、もしその人が生前、
情熱的で、やかましくて、周囲を巻き込み続ける人だったらどうだ。
その人生を、
“葬儀っぽい葬儀”で締めくくることは、本当に誠実なのか。
そこから出てきたのが、
「パッション方式の葬儀」という発想だった。
奇をてらったアイデアではない。
型を疑い、前提を壊した先にしか出てこない、ごく自然な結論だ。
-
オリジナリティは生成されない。
拒絶される。
それを使わない。
それをやらない。
それに従わない。
この否定のプロセスを通らない限り、
どれだけ最新のAIを使っても、
出てくるものは既視感を超えない。
田中友規と伊丹谷大介の対話が、
不格好で、非効率で、ときに不快なのは、
この否定を省略しないからだ。
-
「っぽいこと」をやめると、不安になる。
正解がない。
保証がない。
AIもPinterestも助けてくれない。
だがその瞬間、
思考はようやく身体に戻ってくる。
気持ち悪さ。
違和感。
言葉になる前の引っかかり。
AIが最も苦手とする領域だ。
-
これはAI批判ではない。
ツール否定でもない。
思考を放棄したまま、
思考した気になっている人間への批評だ。
テキストでここまで揺さぶられたなら、
次は対話そのものを見てほしい。
洗練されていない。
スマートでもない。
だが、「っぽいこと」を拒絶し続ける
生の思考プロセスがそこにはある。
-
▶ 関連動画
田中大介の放送室-34-「っぽいことをすな!」